生まれた時から、彼は特別な存在だった。
神の子であるオルフェウスを、周囲の人間はみな畏れ敬ったが、一人の人間として見てくれた者はいなかった。
父王ですら、自分を息子というよりも、女神カリオペからの賜りものと認識していた節があり、邪険にされた訳ではないが、顔を合わせる事すら稀で、親子の情愛など無きに等しい。
ただ一人、傍にいてくれたのは、唯一の兄と呼べる存在のみ。
オルフェウスのこれまでの人生は常に、孤独という文字に彩られたものだった。心を許せる友も、恋人もなく。
そんな風であったから、今まで多くの人々を不快にさせた不遜で高慢な物言いも、決して悪意あっての事ではない。ただ、他人に合わせる事が苦手で、本心を正直に口にしているだけに過ぎない。
彼らのように、オルフェウスの言動に顔を顰める事もなく、親しげに話しかけてくる人間には、この船に乗り込んで初めて出会った。故に正直、どうすれば良いのか、よくわからない。
無論、他の多くの人間からは相変わらず、好かれてはいない事もわかっている。
それは容易く他者に迎合しないオルフェウスの性格のみならず、彼の存在そのものに起因しているという事も。
 |
多くのアルゴナウタイは、ヘラクレスやアタランテのような、傍目にも明らかな豪傑か、或いは翼人兄弟のように、特殊な力を持っているかだ。
オルフェウスには、彼らのような頑健な肉体もなければ、振り回せる剣もない。それが多くの英雄達が、彼に対して侮りの感情を抱く元となっている。
それがわかっていても、オルフェウスは何ら自らを恥じる様子は見せなかったし、彼らと変わらず堂々とした態度で振る舞った。そうした態度が尚更、周囲の反感を買う。
だが誰に嫌われようと、彼がそんな事を気にした事は一度もなかった。
「全くだ。ここは場末の酒場ではないぞ」
その時、部屋の隅から飛んできた声に、オルフェウスは柳眉(りゅうび)を僅かに顰めたが、それだけだった。
不機嫌そうにこちらを見たのは、アテナイの王、テセウスである。
その武勲はヘラクレスと並び称される程の勇士だが、オルフェウスへの態度は、彼とは天と地ほども異なっていた。
「これは戦士の為に造られた船、歌ったり踊ったりする為の舞台ではない」
こちらを不快そうに見る目の中には疑いようもなく、オルフェウスに対する負の感情が見て取れる。
何事にも鷹揚(おうよう)なヘラクレスとは違い、生来から生真面目なテセウスは、音楽をかき鳴らす事しかできないオルフェウスが、英雄の一人として冒険行に参加した事を、未だ認め難く思っているようだった。
そんな態度を取られる事にも慣れているオルフェウスは、表面上は怒りを見せる事はなかったが、母親譲りの美声で、きっぱりと言葉を返す。
「確かに僕には、貴方がたのように剣を振るう事も、弓を射る事もできはしない。だけど僕にだって、武器と言えるものはある。……この竪琴と、この声がね」
オルフェウスの手が、誇らしげにそれらを撫でた。
テセウスの眉根が寄せられる。
それを取り成すように、ヘラクレスが言った。
「ふっ、まあ良いではないか。オルフェウスが俺達の一員として選ばれたのならば、そこにはそれだけの意味があるという事だ」
戦士の中の戦士たるヘラクレスは、あまり物事を深く考えるたちではない。しかしそれ故に、オルフェウスの本質を、的確に理解していた。
口では何を言っても、彼の瞳は神泉の如く澄んでおり、それを見ただけでオルフェウスが邪悪な人間ではない事は示されている。ヘラクレスにしてみれば、それだけで仲間と認める充分な理由になる。
何よりも、悪の心を持つ者に、あのような美しい音楽が作り出せるわけもない。
おそらくアタランテやゼーテス、カライスも、同じ気持ちを抱いている筈だ。
「そうさ。剣や弓が必要なら、使える者は他に大勢いるんだからね」
弓を掴んで言った女狩人の言葉に、ボレアスの息子達が同意する。
「だけど竪琴を弾いて歌を歌えるのは」
「オルフェウスだけなのさ!」
彼らの言葉に、オルフェウスは、ちらと笑みを含む。
けれどそれを気取られないように、軽く指先を動かした。
流れ出した音色に、その音の届く限りにいた者達が、一斉に手を止めて、耳を傾ける。それほどの力が、その音にはあった。
 |
最初は単純な旋律を紡いでいた音が、徐々に複雑な和音に変わり、オルフェウスの手元から溢れ出す。
そしてその口からは、歌が。
二つの音色は重なり合い、開いた窓から、海の上へと流れゆく。
神音の導き手の名を冠されるに相応しい演奏に、全ての者が、うっとりと聴き惚れた。
歌いながらオルフェウスは、いつもそうするように、この指と声を自らに与えたもうた女神へと思いを馳せる。
誰あろう、母カリオペ――音楽と芸術を司る歌神に。
未だ生まれて一度も、その姿を目にした事のない母。
けれど自分が、他ならぬ彼女の息子であるという矜恃は、常に揺るぎ無いものとしてオルフェウスの根幹をなしていた。
自分は、音楽に愛されて生まれてきたと。
この船に乗り込んだのもまた、その誇りの為と言っても過言ではない。
これまで、どの国の、どんな場所であっても、オルフェウスの歌は喝采と共に受け入れられてきた。
けれど、それでは足りない。
自分の技量、自分の力量、果たして自分のこの指と喉に、どれ程の事ができるものなのか。それを青年は試したかった。
アルゴー号の往く海は広く、世界もまた然りである。
誰もが認めた、この冒険行の中でなら、きっとそれを証明する手立てもあるだろう。
そしてオルフェウスが、より一層、深く声を張り上げようとした時だった。
耳をつんざく落雷が、全ての音を打ち消した。
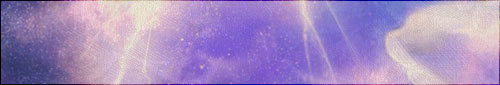
船が大きく揺れ、物の割れる音と悲鳴が木魂する。
オルフェウスは咄嗟に、取り落としそうになった竪琴をしっかりと掴んだ。
「なんだ……!?」
窓から外を覗いて、息を飲む。
つい先刻まで晴れていた空は、今はくまなく黒い雲に覆われていた。
大波が船に襲い掛かり、アルゴー号を大きく揺らす。
楽しげに舞っていた風の乙女の姿も、もう見えない。
「おかしいね」
「これは自然の嵐じゃない」
つい先刻までの、悪戯めいた表情を綺麗に掻き消して、真剣な眼差しでボレアスの子達が言葉を紡ぐ。
その時だった。
遙か彼方から、美しい歌声が聴こえてきたのは。
